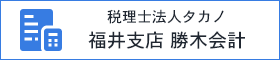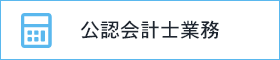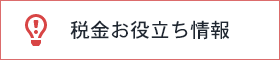記事投稿日:2013.09.12
企業の利益水準が10年位の経過で見ると顕著に下降する傾向を示している場合、その典型的原因のひとつに人権費の増加があります。
人件費の増加原因
このような人件費の増加は、次のように“年功賃金”と“高齢化”が結びついて生じる場合が多いと言えます。
| ①処遇制度の基軸として「職能資格制度」が使われ、「資格が上がれば賃金も上がる仕組み」になっている。
②本来は職務遂行能力が上がれば等級が上がる「職能資格制度」が、運用の甘さで実際には年功的運用になっている。 ③高齢化が進み、高資格者が増え、したがって総額人件費が増えている。 |
視点を変えれば、“年功賃金”ではない、
“役割別賃金・成果主義賃金・職務別賃金”など、脱年功型の賃金制度が確立されていないからだとも言えます。
日本経団連・東京経営者協会の2012年度の人事賃金制度実態調査によれば、図表に示す通り、人事処遇制度の基軸を年功的運用実態の可能性が高い「職務遂行能力」としている企業が、管理職で現在30%程度、非管理職で50%超、と全体に脱年功型移行の努力は不十分です。
人事処遇制度の基軸の変化
| 区分 | 企業数 | 企業数を100%とする企業の比率 | |||||
| 仕事職務 | 職務遂行能力 | 役割 | 成果 | 年齢勤続 | |||
| 管理職 | 現在 | 412 | 15.5% | 32.0 | 24.0 | 26.2 | 2.2 |
| 今後 | 398 | 15・3% | 29.6 | 23.9 | 29.9 | 1.3 | |
| 非管理職 | 現在 | 411 | 13.6% | 53.5 | 12.9 | 9.7 | 10.2 |
| 今後 | 397 | 13.6% | 53.4 | 13.1 | 13.9 | 6.0 | |
年功賃金脱出のポイント
年功賃金から脱出するポイントは、
| ①管理職・非管理職に関わらず、役割・責任を明確にし、業績に応じて給与・賞与を支給する賃金体系とする。
②成果・業績の評価基準を明確にして、公正性・納得性を重視して運用する。 |
ことにあり、通常“脱年功賃金”に移行するには10数年の期間が必要となりますのでなるべく早く着手するべきです。
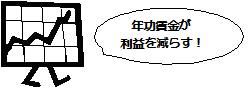
掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。