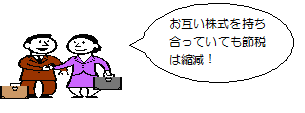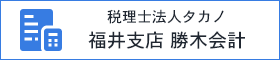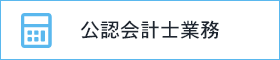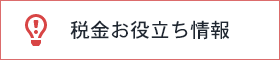自己株式の取得は、それに応じた株主にとっては、①有価証券の譲渡とされ、その譲渡対価(「交付を受けた金銭等の額」から「みなし配当」を控除した額)と譲渡原価の額との差額が譲渡損益と認識され、一方、②交付を受けた金銭等の額が発行会社の資本金等の額を超えた部分は「みなし配当」と認識され、受取配当金の益金不算入の適用を受けることができます。
みなし配当と譲渡損益の仕訳
これを仕訳で表せば次のようになります。
(設例) 株式の取得価額(譲渡原価)60
発行会社から交付を受けた金銭等の額80
発行会社の資本金等の額50
現金預金 80 / 有価証券 60
有価証券譲渡損10 受取配当金 30
*みなし配当に伴う源泉徴収税額は割愛
過日、日本IBMグループが自社株購入で赤字を作り出し、連結納税と組み合わせて過去最大規模の4,000億円もの課税回避をしたとの報道がありました。
国税当局は、これらの行為は「租税回避行為」にあたるとして更正処分に踏切ったようです。一方、IBM側は、法人税法の規定に従って処理したまでで、「合法的な節税」であると主張しています。
自己株式の取得に伴う税務取扱の改正
平成22年度の税制改正において、この自己株式の取得に伴う税務上の取扱が改正されました。改正内容は、次のとおりです。
(1)100%グループ内の法人間の自己株式の譲渡
100%グループ内の内国法人の株式を発行法人に対して譲渡する場合には、譲渡対価を譲渡原価に相当する金額とすることにより、その譲渡損益は認識しないこととされました。前述の設例の「有価証券譲渡損10」は、「資本金等の額10」になるものと思われます。なお、「みなし配当」に関しては、現行法通り、受取配当金の益金不算入制度が適用されます。
(2)上記(1)以外の法人間の自己株式の譲渡
自己株式として取得されることを予定して取得した株式が自己株式として取得された際に生ずる「みなし配当」については、受取配当金の益金不算入制度を適用しないこととされました。なお、有価証券の譲渡損益の認識に関しては、現行法通り、適用があります。
| お互い株式を持ち合っていても節税は縮減! |
適用は、平成22年10月1日以後の譲渡、取得からです。